
食べ物でも対処したい!これからが本格シーズン 花粉症のはなし

花粉症は国民病!? 日本でスギ花粉症が多いワケ

2月に入り、そろそろ憂鬱な季節が本格的に始まってしまいました。本当に辛いですよね⋯そう、花粉症の話です。

何が憂鬱?と首をかしげた方はラッキーと言えるかも。何しろ、花粉症は日本人のほぼ半分が罹患し、国民病とさえ言われているのですから。
前のシーズンまでは何ともなかったのに突然ひどい症状が表れた、なんて体験をされた方も多いのではないでしょうか。

花粉症を引き起こす植物は複数ありますが、冬の終わりから春先にかけては主にスギとヒノキが猛威を振るいます。

特にスギは日本固有の樹木なので、この花粉症を発症するのは、基本的に日本で暮らす人だけということ。
ちなみにヒマラヤスギなど、名前にスギとつく樹木は海外にもありますが、生物学的には日本のスギとは違う種類で、日本語へ翻訳した際に生じた言葉の綾と言えるでしょう。実際、ヒマラヤスギによる花粉症はまれにしか起きないとされています。

花粉症という厄介な側面を持つスギですが、一方で幹がまっすぐに伸び、優良な建築資材として重宝されてもいます。そのため特に第二次世界大戦後の復興期には本州、四国、九州の山々に大量に植林されました。ちなみにスギ林の存在は、北海道ではごくわずか、沖縄ではほぼゼロと言われています。

こうして戦後、急激に増えたスギ林から大量の花粉が飛散するようになり、1964年にスギ花粉症が初めて報告され、以降、同様の症状を訴える人が増えていきました。
花粉症全体の数字になりますが、環境省の報告によれば1998年に19.6%だった有病率は、2008年に29.8%となり、2019年にはなんと42.5%にも達し、現在もうなぎ登りの状況。

近年では品種改良により花粉の量が非常に少ないスギが開発され、順次植え替えが進められているものの、完全に置き換わるまでにはかなりの時間がかかりそう。というわけで、スギ花粉症の人が薬やマスクを手放せない状況は、残念ながら今後数十年という単位で続くと考えられています。

花粉症は免疫の誤作動&暴走
とても身近な花粉症ですが、そのメカニズムは意外と複雑で、きちんと説明しようとすれば、専門用語もたくさん使う必要が⋯。
ただ、簡単に言ってしまえばアレルギー反応という言葉にまとめられます。ではアレルギーとは何かといえば、免疫機能の誤作動で、暴走という表現もしばしば使われます。

アレルギーを引き起こす原因物質=アレルゲンが体内に入ると、ヒスタミンという物質が細胞から放出されます。
このヒスタミンは有害な異物などから体を守るために重要な役割を担う物質です。炎症、かゆみ、くしゃみなどは異物を排除しようとする反応なのですが、花粉は人体に対して毒性がなく本来なら無害な物質。それを有害だと免疫系統が勘違いし、ヒスタミンが大量に放出され、花粉症の辛い症状を引き起こしている、というわけです。
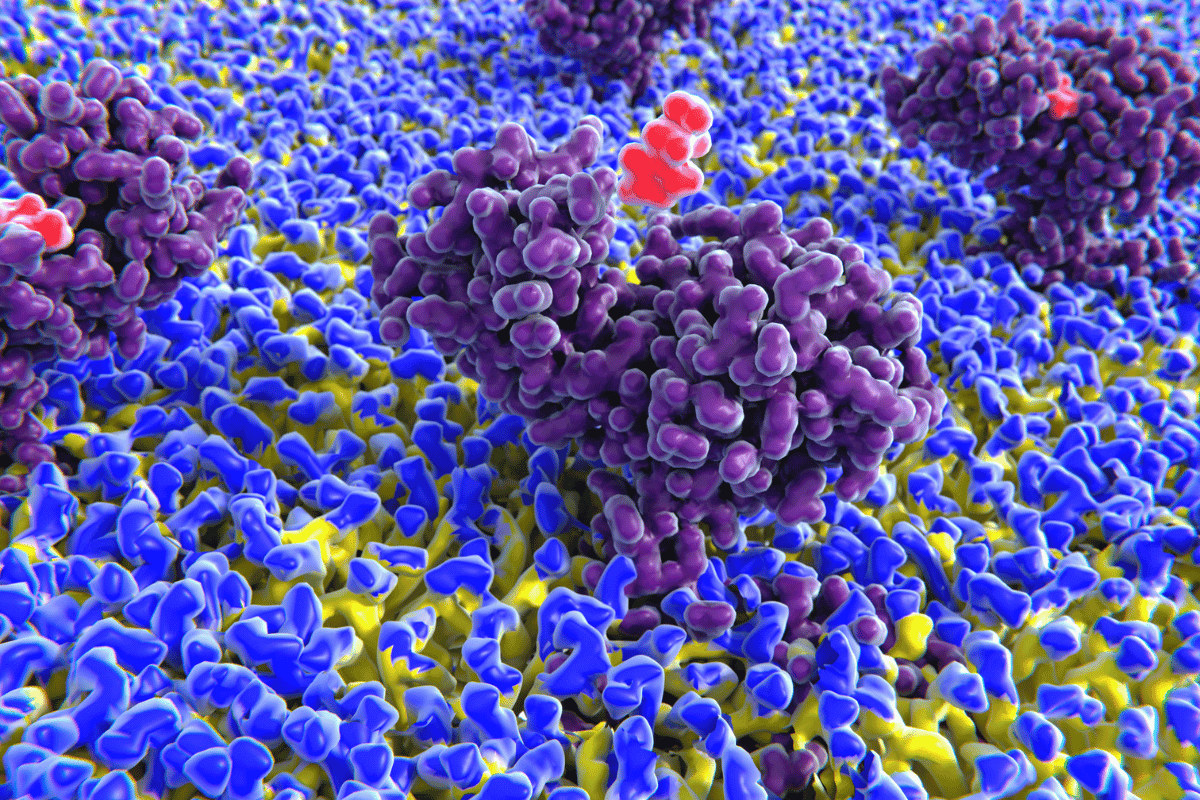
つまり花粉症とは、異物から体を守ろうと頑張った結果、自分自身を傷つけてしまっている、とも言えるわけで⋯ちょっぴり皮肉な話に聞こえますね。

花粉症の歴史 抗ヒスタミン薬はまさにノーベル賞ものの発見!
花粉症の起源については諸説あり、古代ギリシアの記録からも花粉症と思われる症状に関する記述が見つかっているそうです。
花粉症に関する明確な記録で最古のものは1819年。イギリスで刈り取った牧草を乾燥させていた農民たちの間にくしゃみ、鼻水、涙が止まらなくなるという症状が発生し、医学界に報告されました。この報告はジョン・ボストックという医師によりなされたもので、現代の花粉症治療に繋がる第一歩とされています。

その後、似たような症例に関する研究が続けられた結果、1906年にはオーストリアのクレメンス・フォン・ピルケが免疫系の異常反応を突き止め、「アレルギー」という言葉を提唱しました。さらに1940年代に入るとフランスの薬理学者ダニエル・ボヴェが抗ヒスタミン薬を開発。この功績によりボヴェは1957年にノーベル賞を受賞しています。

この薬がなければ、花粉をはじめとする様々なアレルギー物質により、もっと辛い思いをしていた人が世界に何十億といたわけなので、ノーベル賞も納得ですね。
花粉症と食べ物の関係って⁉
現代では抗ヒスタミン薬の服用以外にも舌下療法や、鼻粘膜の焼灼治療など様々な治療法が開発され、実現しています。ただ医療以外で、例えば「普段の生活でも何とかできたら」と思っている方も多いのではないでしょうか?

花粉症は食べ物とも密接な関係があると言われています。一体どんな関係があるのか、まずは、効果的な食べ物を見ていきましょう。
抗炎症作用のある食品
青魚(サバ、イワシ、サンマなど)
これらの食物に多く含まれる、オメガ3脂肪酸には炎症を抑える効果が認められているそうです。

腸内環境を整える食品も効果的
実は腸内細菌が免疫にも大きな影響を及ぼしていることがわかっているそうです。

代表格は乳酸菌を多く含むヨーグルト。
また食物繊維が豊富な食品も、腸内の環境を改善するのに役立つそうで、ごぼう、さつまいも、玄米などが、該当します。
ヒスタミンの放出を抑える食品
緑茶など、お茶の中に含まれるカテキン類が効果を発揮することがわかってきたそうです。

では、逆効果となってしまう食べ物にはどんなものがあるのでしょう。
ヒスタミンを多く含む食品
チーズ、ワイン、ビールなどはヒスタミンが多く、アレルギー症状を悪化させることがあると言われています。
トマト

スギ・ヒノキ花粉症のアレルゲンと良く似た構造を持つ物質が含まれており、ヒスタミンを増やす可能性があるため、症状がひどい場合は控えた方がいいと言われています。
ただ必ず起きるというわけでもないので、スギやヒノキの花粉症だからと言って、やみくもにトマト断ちをする必要もないそうですよ。
花粉症と食物アレルギーは関連が深く、スギ・ヒノキ以外でも…

ハンノキ・シラカンバ花粉症では
リンゴ、洋ナシ、モモ、アンズ、ジャガイモ、大豆(豆乳)、ピーナッツ、キウイ、マンゴー、シシトウガラシなど
ブタクサ花粉症では
メロン、スイカ、キュウリ、バナナなど

こうした食品が、各花粉症に対して注意を要する組み合わせとして挙げられています。
残念ながら、いくら食べ物に気を使っても、それだけで花粉症を完全にコントロールすることはできません。

よく言われることですが、ストレスを減らし、しっかりと睡眠を取り、栄養のバランスが取れた食生活を送り、医師の指示に従いましょう。

これまで花粉症ではなかった人も「もしかして」と思ったら、辛くなる前に診察してもらうのがベストです!
最後までお読みいただきありがとうございます。このコラムでは食物にまつわるトピックを毎回 紹介していますので、次回以降もお楽しみに♪
▼こちらの記事もおすすめ!
飲食業界のしごとを存分に楽しみたい人、楽しさと成長できる環境を見つけたい人、ファイブグループでヒトと未来を熱く語る人事と話してみたい人は、ぜひリクルート窓口へご連絡ください!





